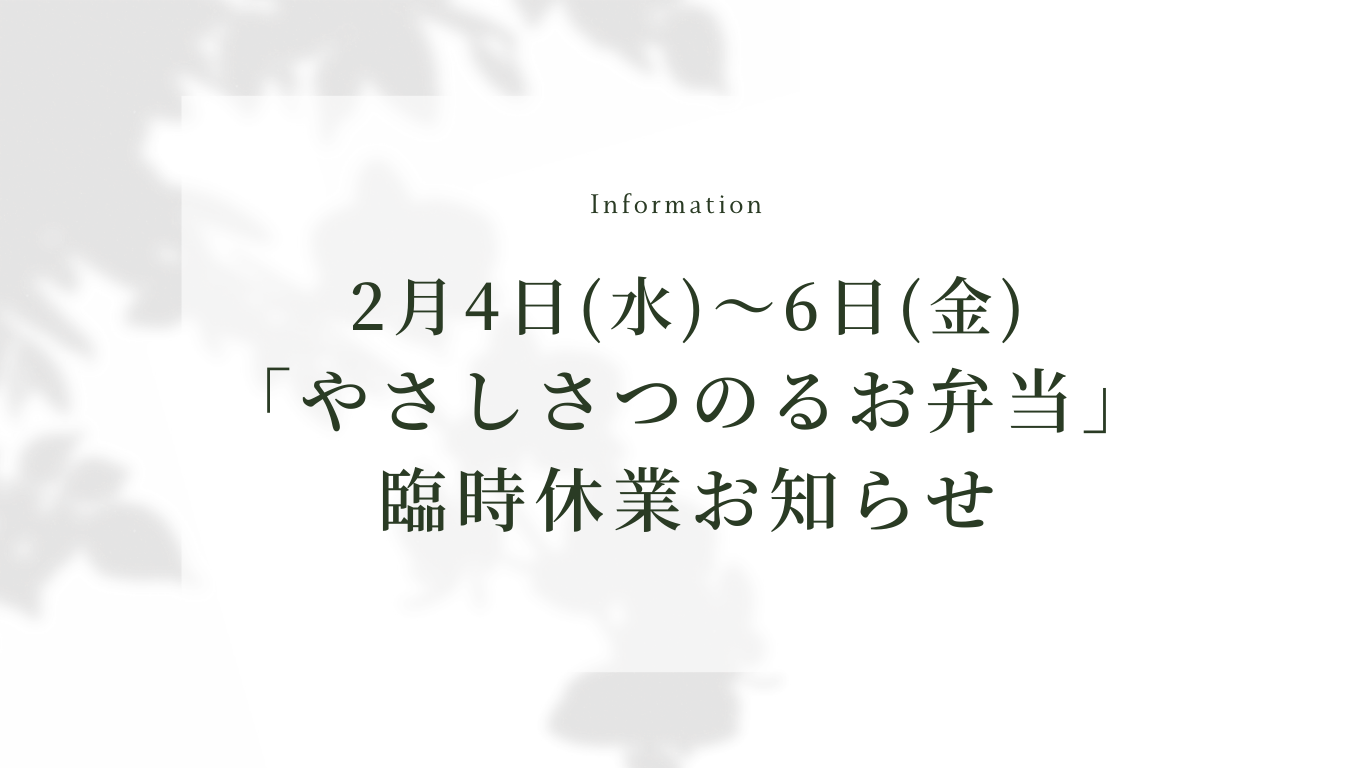【畑から、都農を知るVol.1】竹下政吾さん

〜地域に根付いた農業〜
都農町の総生産に占める農業の割合は16.9%。(都農で働く人の4人に1人は農林水産品の生産者)
これは宮崎県内でも最も高い数値であり、農業が町の暮らしに深く根付いていることを示しています。
スーパーや道の駅には、地元の生産者名が記載された新鮮な野菜や果物が並び、軽トラックやトラクターが町中を行き交う、そんな風景が日常です。
このコラムでは、そんな都農町の農家の皆さんの想いや日々の営みに光を当てていきます。
今回お話を伺ったのは、竹下政吾さん。
ご家族と一緒に、ゴーヤ・なす・イチゴ・かぼちゃなどを育てていらっしゃいます。出荷先は、「道の駅つの」やJA、市場など。
現在は、ゴーヤとナスがちょうど出荷のシーズン。
取材に訪れた日は6月中旬、外気温は33℃でしたが、ハウス内は37℃!過酷な環境下での栽培作業が続きます。
ゴーヤ栽培の裏側
ゴーヤは2月後半に苗を定植し、収穫は4月上旬から7月中旬まで。
実が育ってからも、「脇芽取り」「誘引」「人工授粉」といった細やかな作業が続きます。
※定植=育苗された苗を栽培地へ植え付ける作業
※誘引=茎やつるを支柱に固定して、生長をコントロールすること
竹下さんによると、ゴーヤの蔓は1日で10cmも伸びることがあるそう!
そのため、誘引作業は週に3回も必要とのこと。
ご自身のハウスでは下向きコの字型の誘引法を採用されており、他の農家さんではアコーディオン型にするケースもあるのだとか。
さらに、毎日行う花つけ(人工授粉)も大事な作業です。
「ミツバチなどの昆虫を介して自然に受粉する場合もありますが、確実性を高めるために人の手で授粉させています。」と語ってくださいました。
温度管理にも細心の注意を払いながら大切に育てられたゴーヤは、艶やかで青々としていてとても美味しそうでした。


ナスにも一工夫
ナスは黒ナスと白ナスの2種類を栽培中。
今年は5月20日に定植を行い、6月17日から黒ナスの収穫を開始。白ナスの収穫はもう少し先とのこと。
黒ナスは「PC筑陽」という品種で、濃黒紫色でツヤのある美しい見た目が特徴。
一方の白ナスは「とろ~り旨なす」という品種で、ホルモン剤による人工授粉が必要なのだそうです。
「道の駅つの」で竹下さんのナスを探すと、「農家野郎のガチで旨いなす」とインパクトのあるステッカーが貼られ、味へのこだわりと遊び心を感じます。




農業のやりがいと厳しさ
「都農は穏やかな気候で寒暖差もあり、農作業には適しています。」と竹下さん。
その一方で、自然災害への備えは欠かせません。
台風が来ると、ハウスが飛ばされないようにビニールを外し、作物には頑丈にネットをかけて守る。去った後には一つひとつしっかりと水洗い。
海に近い圃場では塩害も心配されます。
昨年の大雨では、両端に流れる川が氾濫し、植えたばかりのイチゴが全滅してしまったことも。
農業においては「栽培工程の遅れ」が大きなリスクだといいます。
「遅れると、ナスは実を落とし、ゴーヤは伸びすぎてしまう。イチゴも適切な管理ができず害虫にやられてしまう」とのこと。
こうした努力の積み重ねが、日々私たちの食卓に新鮮で美味しい野菜を届けてくれているのだと、改めて実感しました。
「毎日が体力勝負で休みもないけれど、
出荷した作物が道の駅や市場で完売したと聞くと、やっぱりうれしいですね。」
竹下さんの言葉と笑顔に、農業の誇りと情熱を感じました。
今後も都農町で頑張る農家の皆さんの声をお届けしていきます。

都農マリアージュの代名詞とも言える書籍『みんなが喜ぶワインのおかず』(2024年刊)には、ゴーヤの苦みと生姜のピリッとした辛味の組み合わせがクセになる「ゴーヤとガリ」、とろりとしたナスが主役と言ってもいい「豚肉となすの梅生姜焼き」のレシピを掲載しています。ぜひご覧ください。